
コンテンツのネタに困ったら?記事に書くことの探し方

- 記事ネタを炙り出す2つの方法
- 方法1:ニーズからのアプローチ
- 方法2:コンテンツからのアプローチ
- この2つの方法を効率よく組み合わせる方法
コンテンツのネタに困ったら?記事に書くことの探し方
この記事では、記事に書くネタに困っている人向けに、
- 記事ネタを炙り出す2つの方法
- この2つの方法を効率よく組み合わせる方法
を解説します。
なお、この記事はオウンドメディア向けのハウツーであり、性質が異なるブログでの応用はできませんので、
ブログの場合は、「ブログに何を書く?書くことがない時に一般人でもできる記事ネタの探し方とコツ」をご参考ください。
記事ネタを炙り出す2つの方法
オウンドメディアを運用するにあたり、テーマは予め決められており、それをもとにキーワードの抽出も行われるので、基本的に、コンテンツのネタに困ることはありません。
一方で、事前のキーワード抽出を行わなかったり、その作業が不十分だったりすると、途中から記事に書くネタに困ります。
途中の作業に問題があるため、理想的には、最初からやり直した方が望ましいですが、予算や時間的にそれが非現実的な場合が多いので、ここでは、記事ネタを炙り出す2つの方法を紹介します。
方法1:ニーズからのアプローチ
メインテーマはあるものの、サブテーマや論じたい具体的なテーマがいまいち定められていない場合はこのアプローチが役に立ちます。
たとえば、SEOについて書きますが、どのような流れでSEOのどの部分を具体的に書きたいかわからない時です。
こういう時は、キーワードの検索ボリューム=ニーズからアプローチします。
具体的には、「キーワードを効果的に選定するコツ」に沿ってキーワードを抽出・リストアップし、「キーワードのグルーピンと選定のやり方」に基づき、キーワードをグルーピングした上で、選定することです。
この方法のメリットとしては、上位獲得の可能性が高く、早い段階でアクセスの獲得が見込める結果、コンバージョンも早く取れることです。
一方で、デメリットとしては、一つのテーマ、トピックを論じるのに、網羅性に欠ける可能性があるという点です。なぜならば、必要な論点のキーワードの検索ボリュームが少ないという可能性もあるからです。
例えば、SEOをトピックに漏れなく論じていくのに、「キーワードのグルーピング」をもカバーする必要がありますが、「キーワード グルーピング」の検索ボリュームが少ないと、「キーワードのグルーピンと選定のやり方」の段階で削除されてしまう可能性があります。
方法2:コンテンツからのアプローチ
キーワードうあキーワードの検索ボリュームをひとまず一旦無視し、テーマを漏れなく論じるのに、どのような記事が必要かを先に考えるアプローチです。
こういう時はマインドマップで、テーマを分解していくと、より整理しやすいです。
このような方法のメリットとしては、網羅性を担保できることから、実にユーザーフレンドリーである点です。
一方で、デメリットとしては、上位獲得がやや実現しづらく、アクセスを獲得できるようになるまで時間が掛かるといったところです。ただし、この辺りは、「キーワードを効果的に選定するコツ」で紹介している「事後アプローチ」で修正すれば問題はありませんので、あまり気にする必要はありません。
この2つの方法を効率よく組み合わせる方法
ハイブリッドアプローチでも言いましょう。
まずは、後者である「コンテンツからのアプローチ」で、①全体の構成や②必要な記事を一旦決めます。
記事のタイトルも仮で良いですし、まずは、どのような記事が必要なのかを書き出します。
③仮のタイトルと記事内容から暫定の④メインキーワードを決めます。
これらの④メインキーワードをもとに、「ニーズからのアプローチ」でキーワードをリストアップしてグルーピングします。
その後、①の全体構成と②の必要な記事に合わせて、キーワードを当てはめていき、③のタイトルを微修正していきます。
こうすることにより、早い段階でアクセスの獲得が見込めると同時に、網羅性の担保もできます。
この2つの方法を組み合わせれば、記事ネタに困ることはありませんので、残りはPDCAの段階において、状況に合わせて「事後アプローチ」でキーワードとタイトルを微修正するだけです。
関連記事
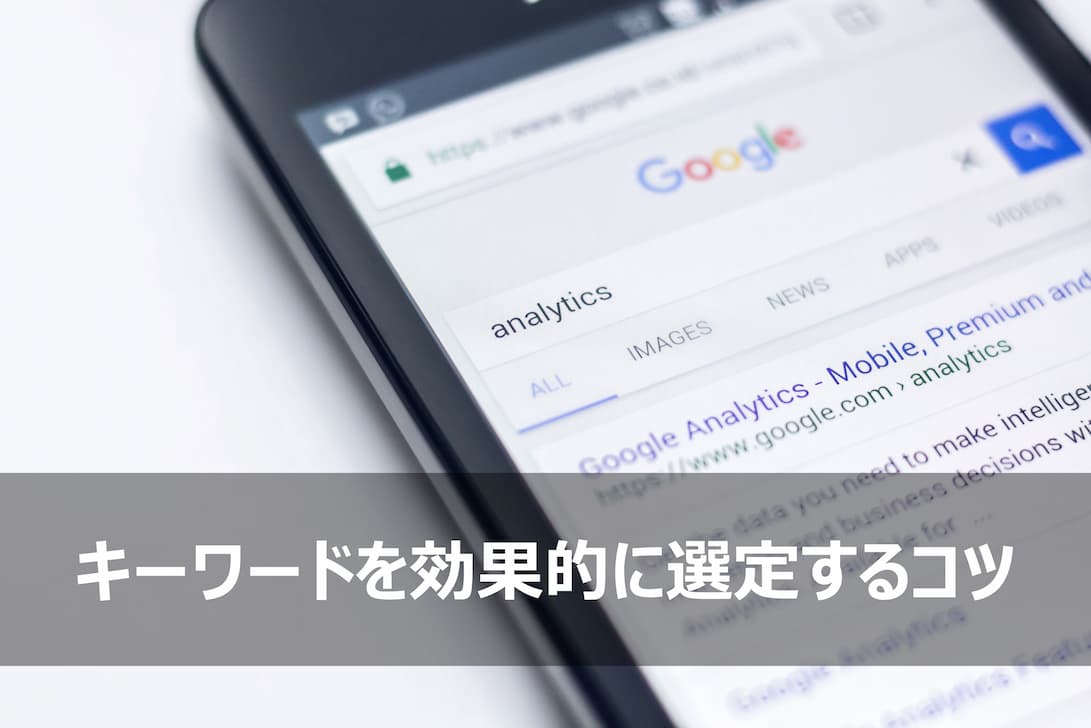
キーワードを効果的に選定するコツ|リストアップする4つの方法

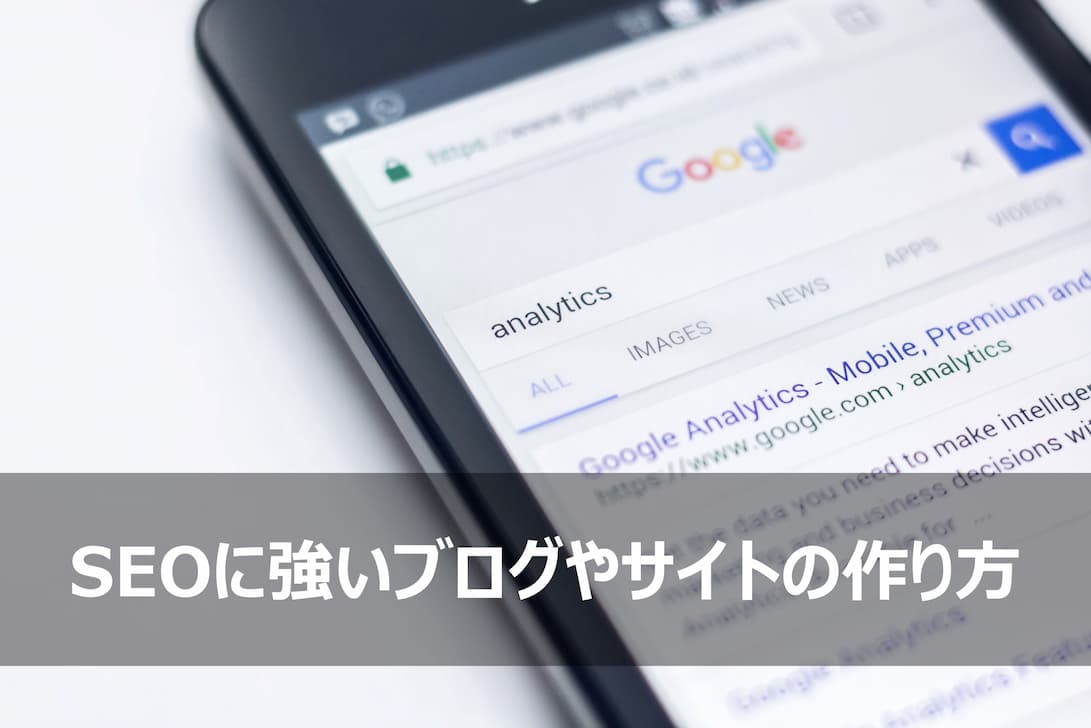
SEOに強いブログやサイトの作り方|オウンドメディア運営とコンテンツ作成の鉄則

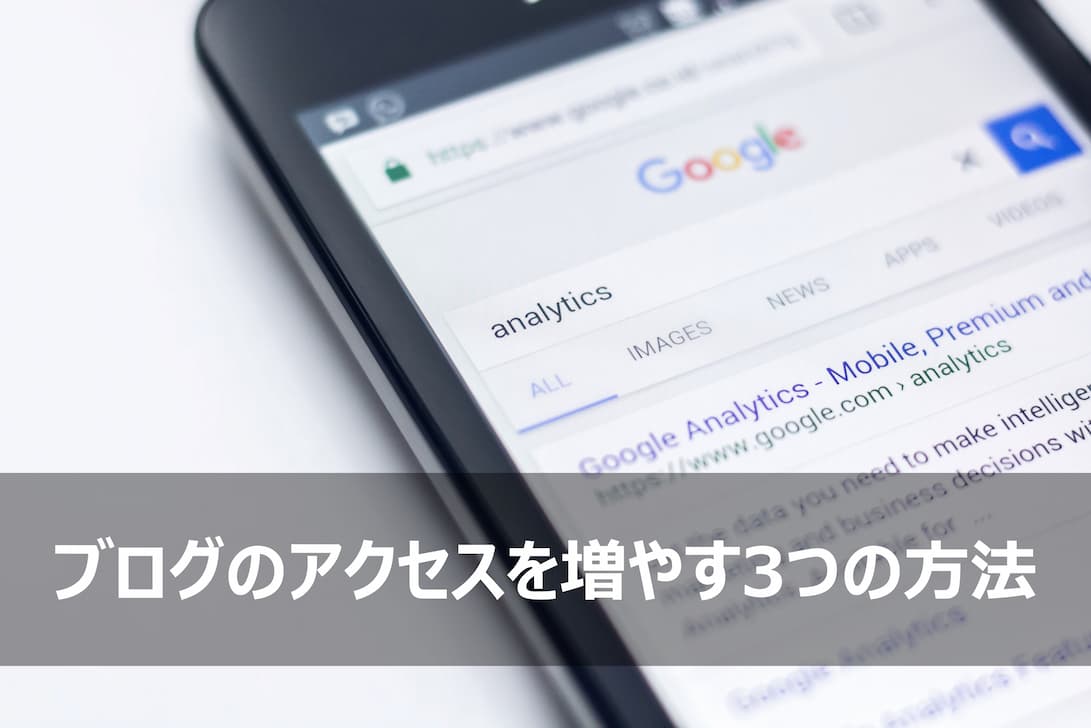
ブログのアクセスを増やす3つの方法|PV増えない時に自分でできるSEO対策

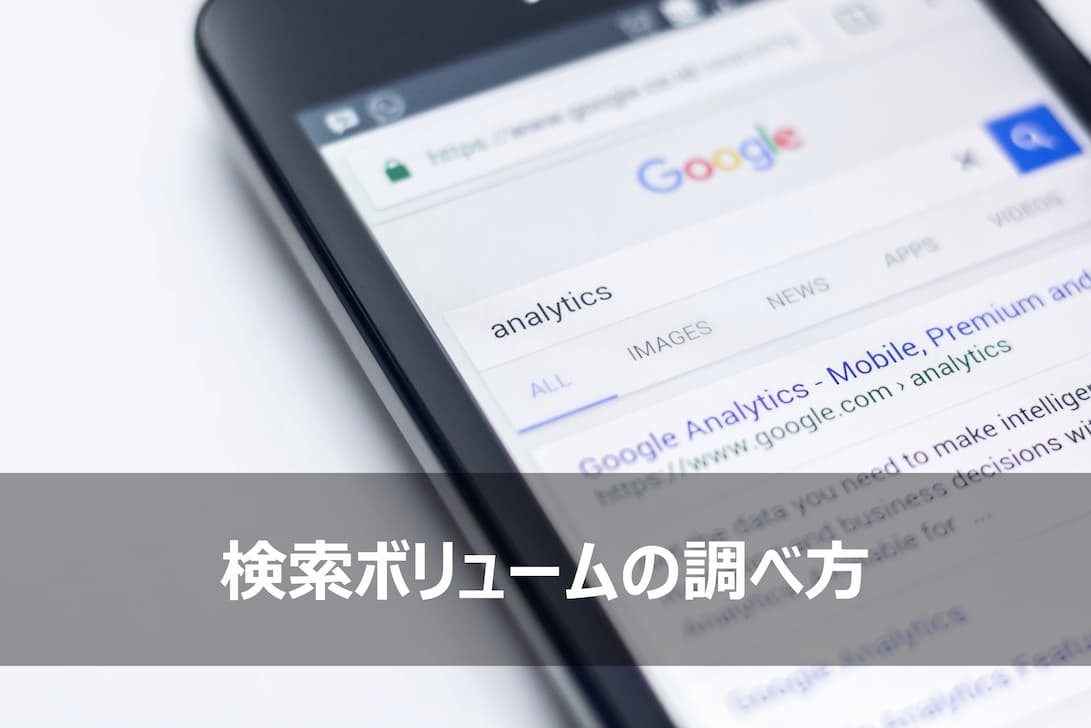
検索ボリューム(google検索数)の調べ方|キーワードプランナーとそれ以外の使い方

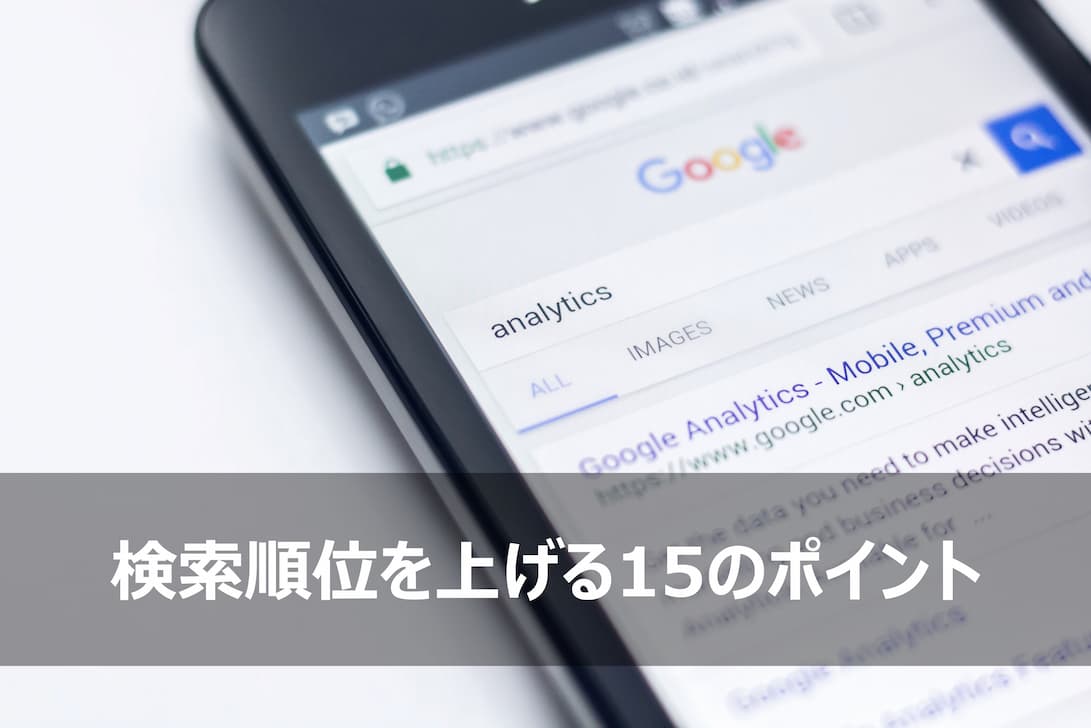
検索順位を上げる15のポイント|誰でも簡単にGoogle検索の上位表示を可能にするコツと裏技

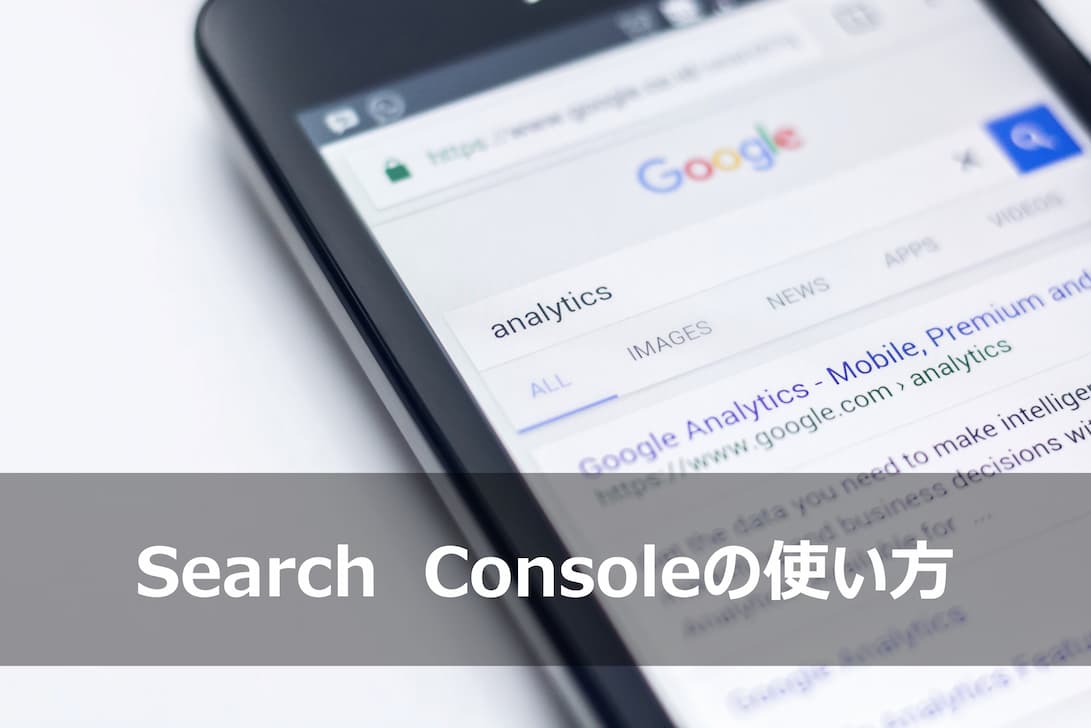
グーグルサーチコンソールの使い方|登録・設定から見方まで解説

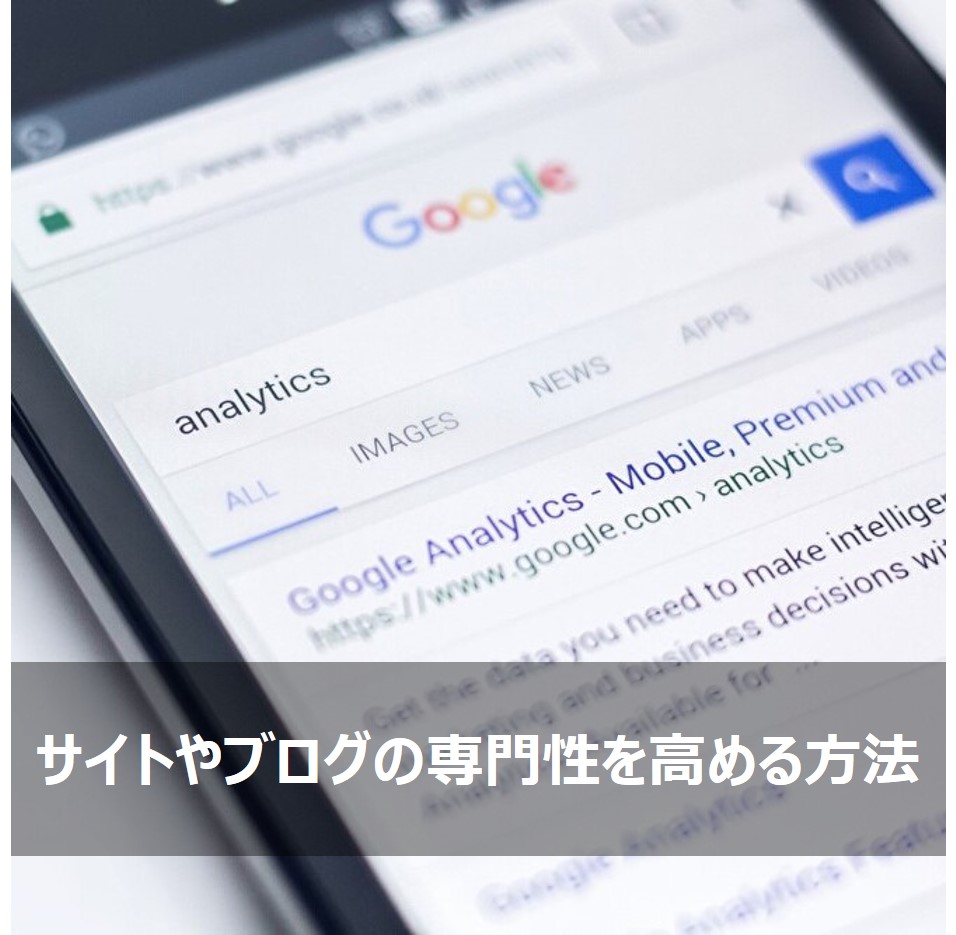
サイトやブログの専門性を高める方法と手順~検索順位との関係と上位表示のためのコツ


Google検索結果から削除する|検索されないようにするサーチコンソールの申請方法

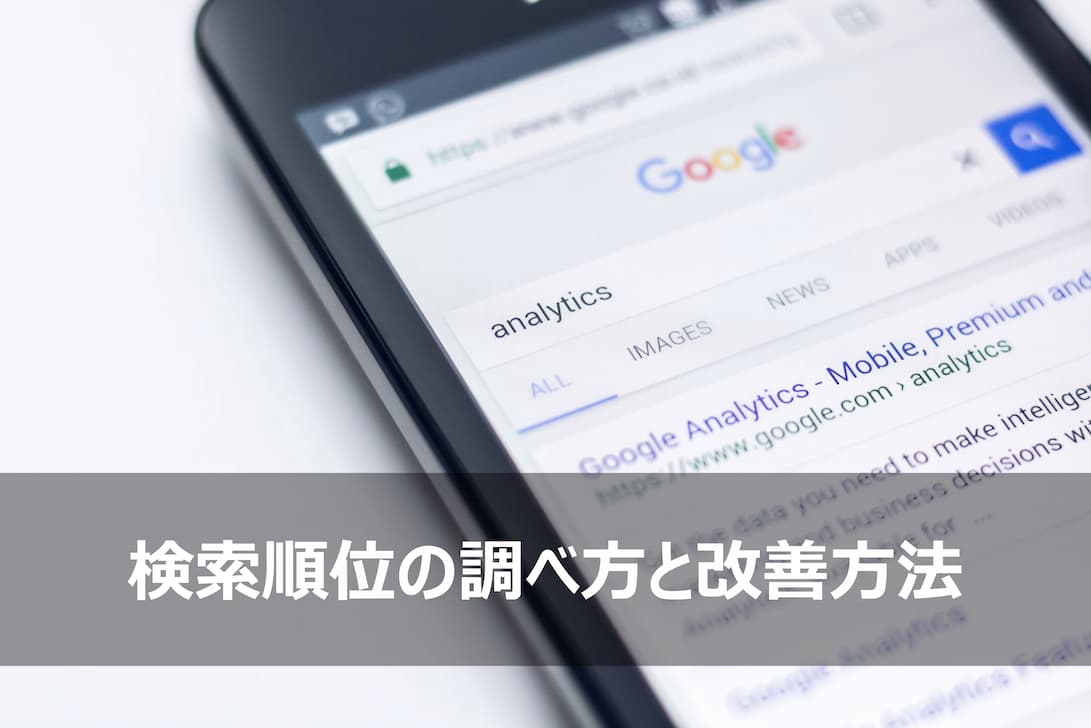
検索順位の調べ方と改善方法|キーワードの順位をチェックする方法と無料ツールの紹介

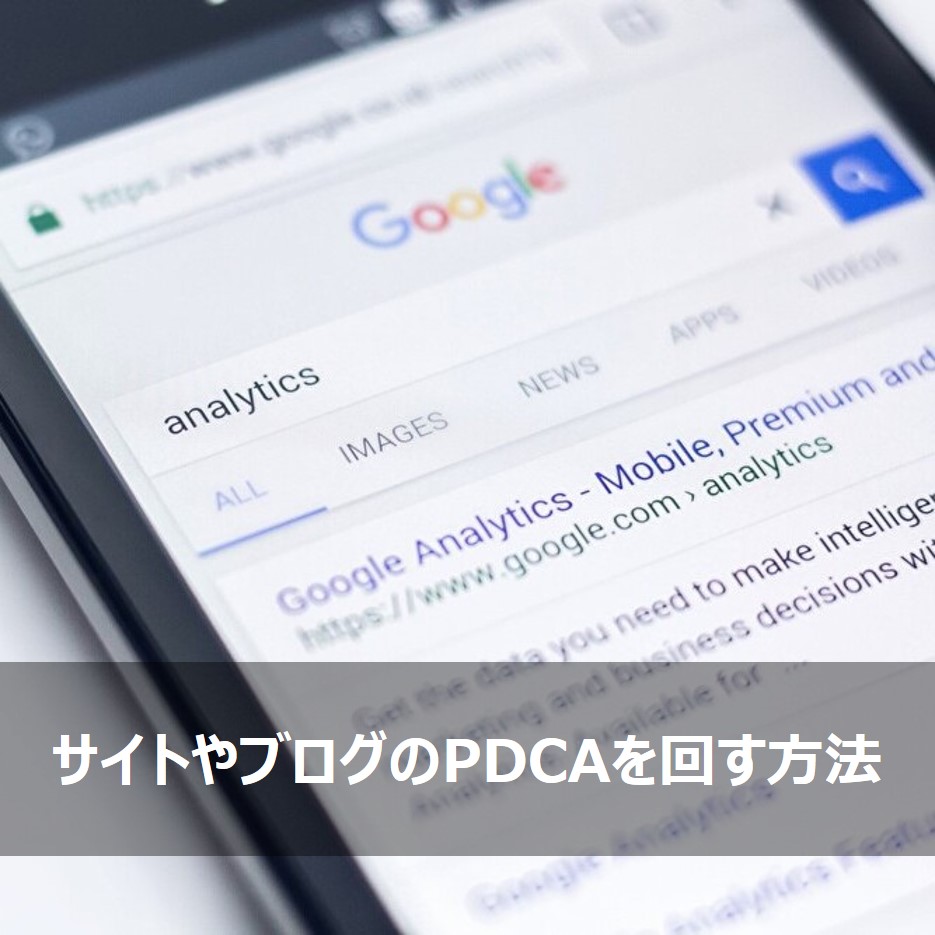
サイトやブログのPDCAを回す方法|事例から見るクリック率やUIなどの改善方法


ページのクリック率が低い場合の対応と上げるコツ|サーチコンソールから対策すべき記事とクエリの見つけ方と改善する方法

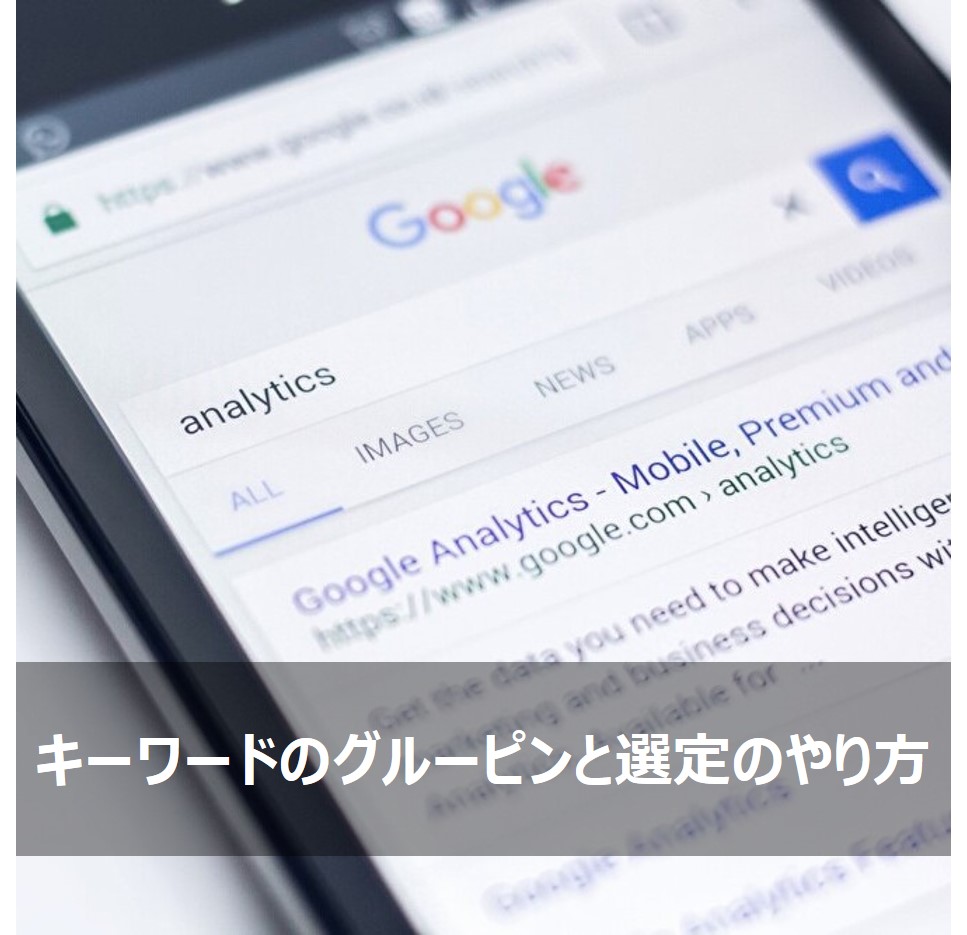
キーワードのグルーピンと選定のやり方|キーワード分類から記事への入れ方まで解説


キーワードマッピングでSEO対策記事を可視化|無料マインドマップツールでできるキーワードマップの作り方


SEOに強いWEB記事構成案の作り方|検索意図を重視した企画案のコツ

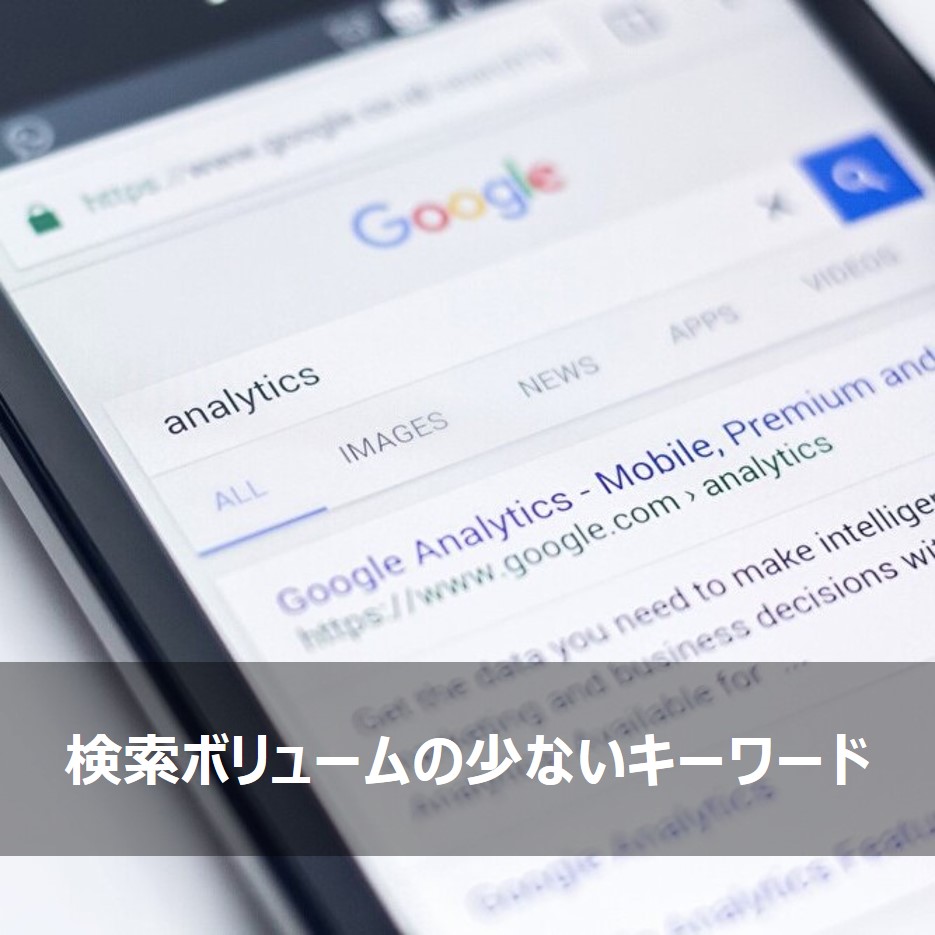
検索ボリュームの目安から考える検索ボリュームの少ないキーワードのSEO対策

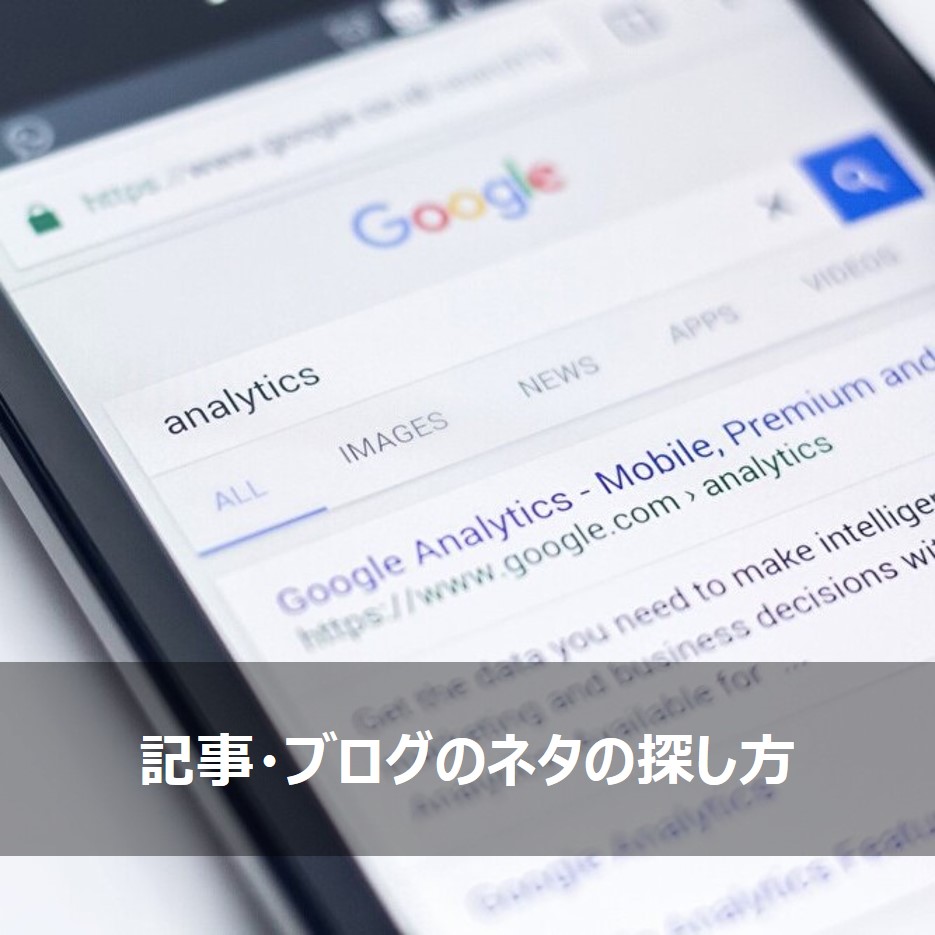
ブログに何を書く?書くことがない時に一般人でもできる記事ネタの探し方とコツ


コンバージョン

ピックアップ記事
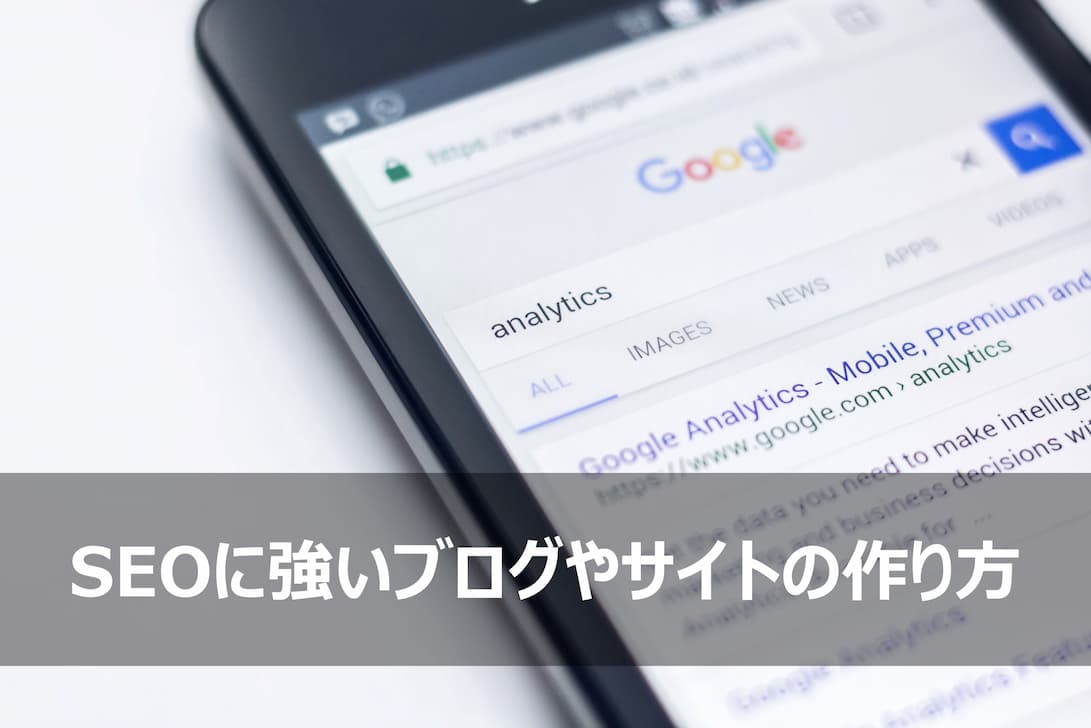
SEOに強いブログやサイトの作り方|オウンドメディア運営とコンテンツ作成の鉄則

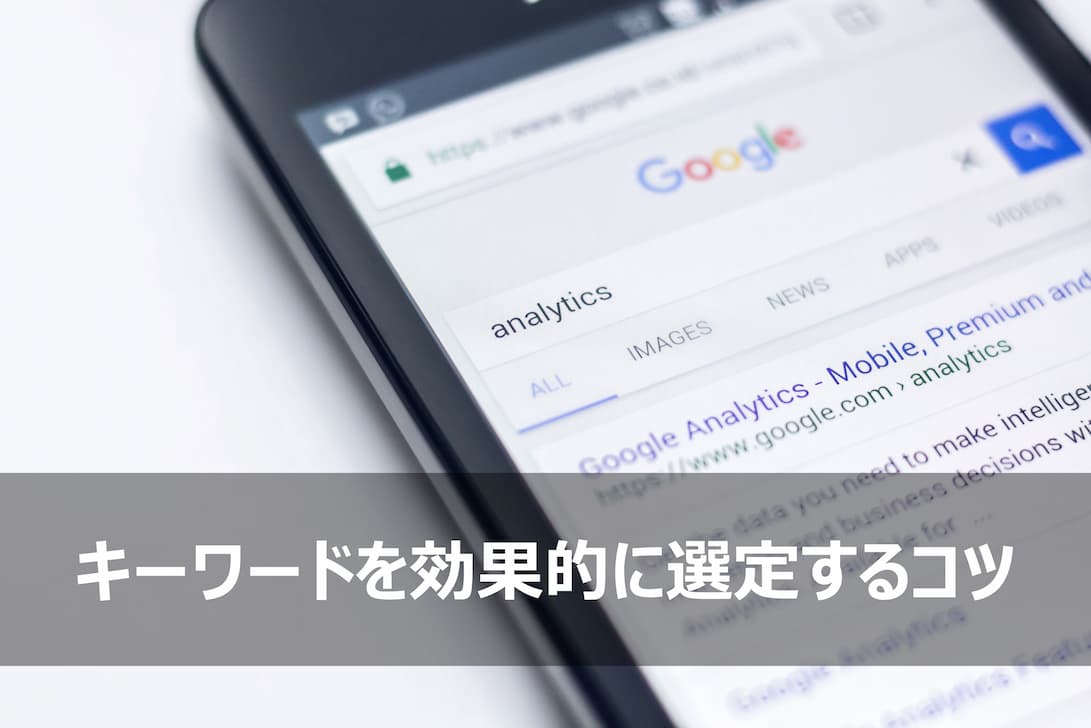
キーワードを効果的に選定するコツ|リストアップする4つの方法

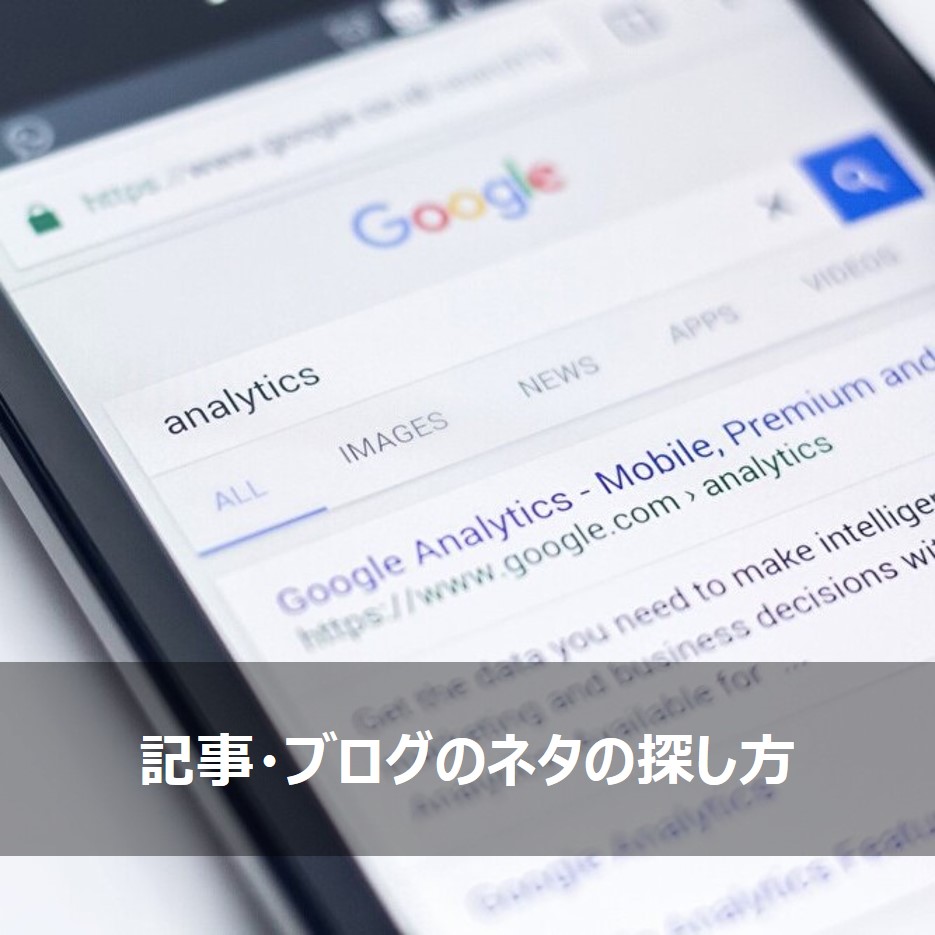
ブログに何を書く?書くことがない時に一般人でもできる記事ネタの探し方とコツ


オウンドメディアの公開記事数の目安|コンテンツの量と質から考える最適な記事数

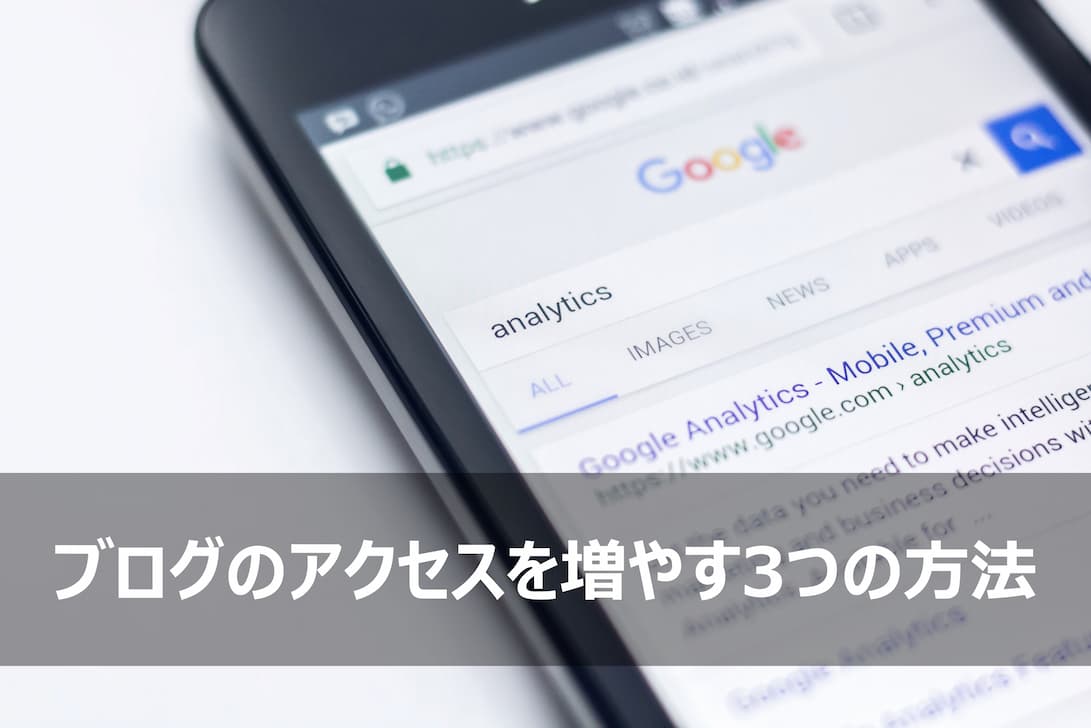
ブログのアクセスを増やす3つの方法|PV増えない時に自分でできるSEO対策




